またまたXTC…
今まで「オレンジズ・アンド・レモンズ」「スカイラーキング」「ザ・ビッグ・エクスプレス」と遡って来た。
となると、今回の「レコード評議会」は当然こうなる。
Mummer
UK盤(1983年)
Virgin
V2264
Side1:V 2264 A - 2U - 1 - 1 - 3 SOUND CLINIC
Side2:V 2264 B - 2U - 1 - 1 - 5 JONZ



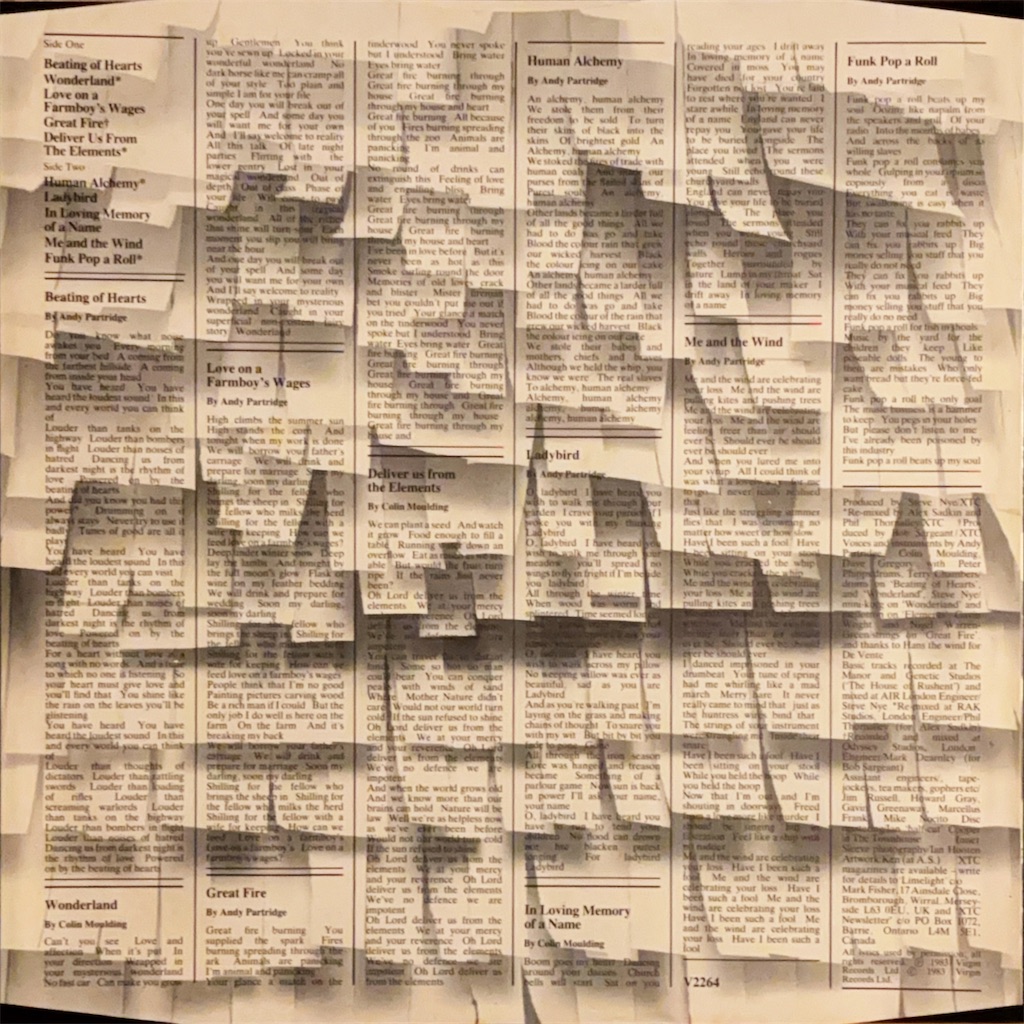


Side1
1. Beating Of Hearts
2. Wonderland
3. Love On A Farmboy's Wages
4. Great Fire
5. Deliver Us From The Elements
Side2
1. Human Alchemy
2. Ladybird
3. In Loving Memory Of A Name
4. Me And The Wind
5. Funk Pop A Roll
一般的に低迷期と言われる頃の作品「ママー」(6枚目のアルバム)。
Mama(Mother)では無く、Mummer。
「ママー(Mummer)」とは何か、ChatGPTに聴いてみたら、こんなに詳しく回答が返ってきた。
「ママー(Mummer)」とは、イギリスの伝統的なフォーク劇である「ママーズ・プレイ(Mummers' Play)」の演者を指します。「ママーズ・プレイ」は、中世から続くイギリスの民間伝承の一部であり、特にクリスマスやその他の祝祭日に行われることが多いです。
1. ママー(Mummer)の特徴
① 仮装と仮面
- 演者(ママー)は、しばしば仮装をし、顔を隠すための仮面を着けます。これにより、彼らの正体が分からないようになっています。
② 劇の内容
- ママーズ・プレイの内容は様々ですが、一般的には善と悪の戦い、死と復活、病気と治癒などのテーマが含まれます。これらの劇は、寓話や民間伝承、宗教的なモチーフに基づいています。
③ 即興性
- ママーズ・プレイは即興性が高く、台本があったとしても、演者が即興でセリフを追加したり、変更したりすることがよくあります。
④ 地域性
- イングランド全土に広がっているため、地域ごとに異なるバージョンの劇があります。それぞれの地域で独自のキャラクターやストーリーラインが発展しています。
2. 歴史
① 起源
- ママーズ・プレイの起源は正確には不明ですが、中世ヨーロッパにさかのぼります。初期の形式は、異教の儀式や収穫祭に関連していたと考えられています。
② 発展
- 17世紀から19世紀にかけて、ママーズ・プレイはイギリスの多くの村や町で盛んに行われました。この時期に、劇はクリスマスの伝統行事として確立されました。
③ 現代のママーズ・プレイ
- 現代でも、イギリスの一部の地域ではママーズ・プレイが行われています。伝統を守りながら、新しい要素を取り入れることもあります。
3. 文化的意義
① コミュニティの絆
- ママーズ・プレイは地域社会の一体感を高める役割を果たしてきました。村や町の住民が一緒に劇を作り上げることで、コミュニティの絆が強まります。
② 伝統の継承
- ママーズ・プレイは、地域の歴史や文化を次世代に伝える手段としても重要です。若い世代が参加することで、伝統が生き続けます。
「ママー」は、このような豊かな文化的背景を持つ伝統的なフォーク劇の演者を指します。彼らのパフォーマンスは、歴史と文化を反映した重要な役割を果たしてきました。




上段:現在のママー・プレイ
下段:中世のママー・プレイ
で、ついでにこのアルバム「ママー(Mummer)」についてもChatGPTに聴いてみたら、こんなに詳しく回答が返ってきた。
「ママー(Mummer)」は、イギリスのロックバンドXTCの6枚目のスタジオアルバムで、1983年8月30日にヴァージン・レコードからリリースされました。このアルバムは、バンドが1982年にライヴ活動を引退した後に録音された初のアルバムです。
1. アルバムの制作背景
- フロントマンのアンディ・パートリッジが神経衰弱から回復中に制作されました。パートリッジはバンドがスタジオに専念することを決定し、新たな創作意欲が湧きました。
- ドラマーのテリー・チェンバースはライヴ演奏を好んでいたため、スタジオ専念の方針に不満を持ち、アルバムの制作途中でバンドを脱退しました。彼の後任にはピート・フィップスが起用されました。
2. アルバムの制作とリリース
① プロデューサー
- アンディ・パートリッジは、ジャパンの「錻力の太鼓(Tin Drum)」の作品に感銘を受け、スティーヴ・ナイをプロデューサーに迎えましたが、ナイのスタイルはXTCには適していないと感じるメンバーもいました。
② レコーディング
- 最初の録音セッションは1982年9月に行われましたが、ヴァージン・レコードはアルバムにヒットシングルがないと考え、追加の楽曲制作を要求しました。
- 当初はボブ・サージェントをプロデューサーに迎え、"Great Fire"と"Gold"が制作されました。 "Great Fire"はアルバムの最初のシングルとしてリリースされましたが成功しませんでした。
- "Wonderland"を含むいくつかの曲はセールス強化を目的にアレックス・サドキンとフィル・ソーナリーによりリミックスされましたが、このため予算オーバーとなりました。
③ リリースの遅れ
- ヴァージンはアルバムのリリースを数ヶ月遅らせ、最終的に1983年8月30日にリリースされました。米国では1984年2月にゲフィン・レコードからリリースされました。
3. アルバムの評価
- 「ママー」は批評家から賛否両論の評価を受けました。ローリング・ストーンのJ.D.コンシダインは「XTCの最もアクセスしやすいアルバム」と評価しましたが、ヴィレッジ・ヴォイスのロバート・クリストガウは「これまで以上に洗練され、乾いた音」と批判しました。
- 後年の評価では、AllMusicのクリス・ウッドストラは「バンドのこれまでで最も優れた曲が含まれている」と評価しましたが、アルバム全体の一貫性が欠けると指摘しました。
4. アルバムタイトルとアートワーク
- アルバムのタイトル「ママー」は、イングランドのウェストカントリーで変装して登場するママーズ・プレイの演者に由来しています。
- 元々のタイトルは「Fruits Fallen From God's Garden」で、デザイン・クリニックのデイブ・ドラゴンに依頼してスリーブアートを制作しましたが、ヴァージンのマーケティングチームに却下されました。
- 2022年5月6日、エイプハウスはアルバムを200グラムのビニールで再発し、元々意図されていたスリーブアートが復元されました。
「ママー」はXTCの転換期を象徴するアルバムであり、バンドのライヴ活動引退後の新しい方向性を示しています。
元々意図されていたジャケット(=インナースリーヴのデザイン)

ということで、ビートルズの様にライヴ活動を止めて、スタジオに専念することになったXTC。
テリーの脱退、レコード会社からの強いセールス要求など、あれこれとありつつ、何とかリリースに漕ぎ着けたアルバムが「ママー」なのだが、さてその内容は?
従来同様、勝手な印象を含めて、各曲を紹介しよう。
A:アンディ・パートリッジ作曲
C:コリン・モールディング作曲
⭐️の数:個人的に好きな度合い(最高で⭐️5つ)
Side1
1. Beating Of Hearts (A)⭐️⭐️⭐️⭐️
アルバム制作途中で脱退するテリーがドラムを叩いている(テリーのドラムはSide1の1と2のみ)。
なかなか凝ったアレンジのアラビア風?エスニックな曲。
ライヴを前提としないスタジオ専念ゆえの曲作りだが、なかなか悪く無い。と言うか、結構良い。
2. Wonderland (C)⭐️⭐️⭐️
セールス強化を目的にリミックスされた曲。
アルバムのリリースに先立って1983年6月24日にシングルリリースされているが、ヒットしなかった模様。
Prophet-5というアナログ・シンセサイザーによるサウンドは、タイトル通り、おとぎの国の雰囲気。
これもライヴでは再現不可能。

3. Love On A Farmboy's Wages (A)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
アルバムリリース直後の1983年9月19日にシングルリリースされている。UKチャート50位とまずまず。
前作「イングリッシュ・セツルメント」に収録されている名曲"Senses Working Overtime"と似た構成と雰囲気のアコースティックな曲。
英国の田舎が感じられる、素直に良い曲。
4. Great Fire (A)⭐️⭐️⭐️
アルバムのリリースに先立って1983年4月22日にシングルリリースされているが、ヒットしなかった模様。
この曲のみボブ・サージェントがプロデューサーであり、そもそもシングル用の曲だったのだろう。
結構大袈裟な作りの曲で、XTCにとって新境地ではあったのだろう。
5. Deliver Us From The Elements (A)⭐️⭐️⭐️
セールス強化を目的にリミックスされた曲。
エスニックな雰囲気の曲で、悪く無い。
リミックス前は単調だったのか?
Side2
1. Human Alchemy (A)⭐️⭐️⭐️
セールス強化を目的にリミックスされた曲。
人間の錬金術?というタイトルの通り、魔術的な雰囲気の曲。
A面もB面も1曲目に今までのXTCとは違った雰囲気の曲を持って来たところに、意気込みを感じる。
2. Ladybird (A)⭐️⭐️⭐️⭐️
ジャズのイディオムで作られた曲で、ブラジル・フレーヴァーもある。アンディの趣味の広さを感じさせる。
ボーカルがアンディでなければ、XTCとは全く思えない。まるでAOR、マイケル・フランクスの曲の様だ。
一般的にXTCに求めるものとは違うのだろうが、曲としては名曲の部類。隠れ名曲。
3. In Loving Memory Of A Name (C)⭐️⭐️⭐️⭐️
アコースティックで趣味の良い響き。
AORだと思って聴くと、そんな感じもする。
コリンの豊かな感性を感じさせ、彼の曲の中でもレベルが高い。隠れ名曲。
4. Me And The Wind (A)⭐️⭐️⭐️
ワルツのリズムにエスニックな変なメロディが乗る。
この曲単体では何とも評価し難いが、アルバムの中にこんな曲はあっても良い。嫌いでは無い。
5. Funk Pop A Roll (A)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
セールス強化を目的にリミックスされた曲。
これぞXTCというギターポップなノリの良い曲(ノリの良さで言えば、XTCの中でもかなり上位)。
パンチの効いた曲なので、アルバム1曲目に置けばセールス的にも良かっただろうに… と思ったりもするが、そうしないのがアンディ(ひねくれ者)なのだろう。
以上、全10曲の集計結果は以下の通り。
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️:2曲
⭐️⭐️⭐️⭐️:3曲
⭐️⭐️⭐️:5曲
ん?低迷期のアルバムじゃないの?
いやいや、先入観無しに聴いてみると、あに図らんや、良い曲が並んでいる。アルバム全体としても良い。
エスニック、異国風、魔術的、牧歌的、英国田舎風、ジャズ・フュージョン、AOR、ギターポップ…
様々な音楽性が散りばめられていて、実験的でもある。
ふと思ったのだが、ビートルズになぞらえて言えば「リボルバー」を軸に「ラバー・ソウル」と「サージェント・ペパー」の要素も加えた様な感じ?
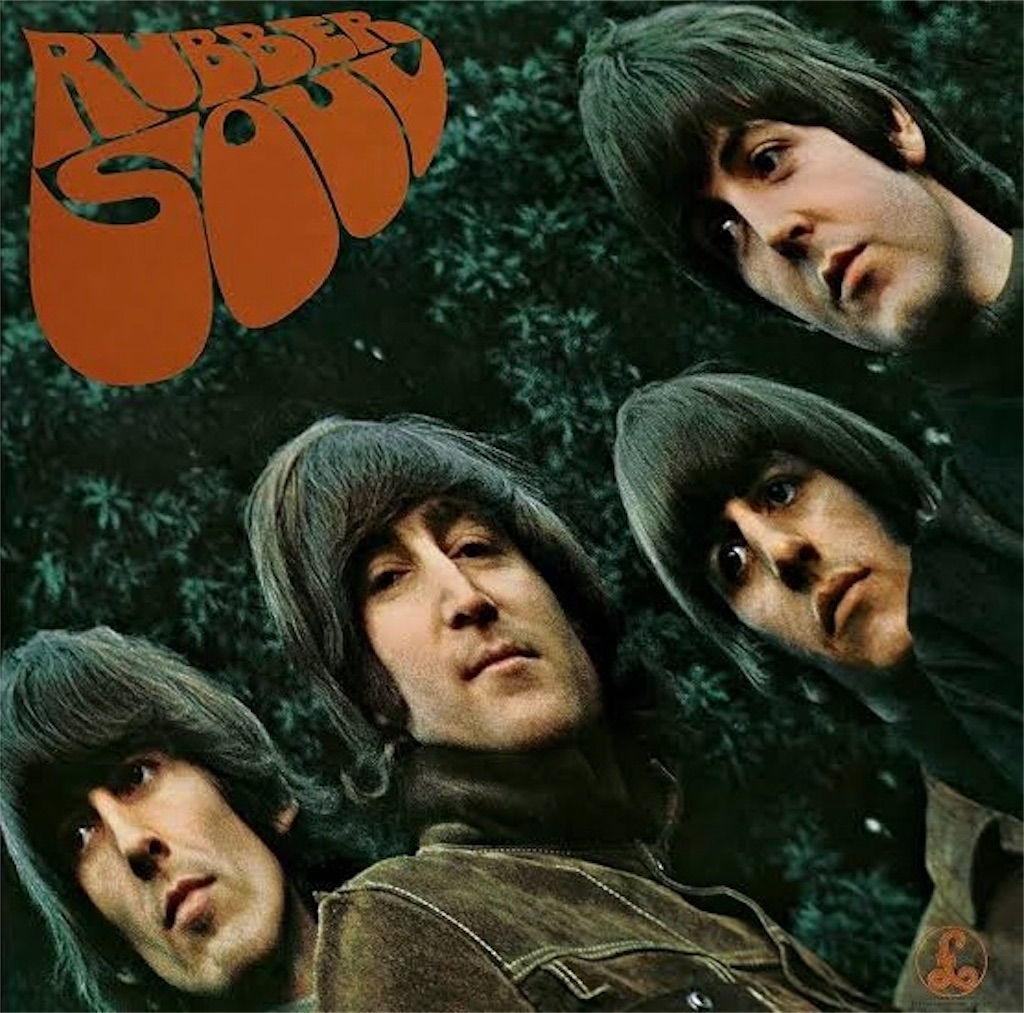
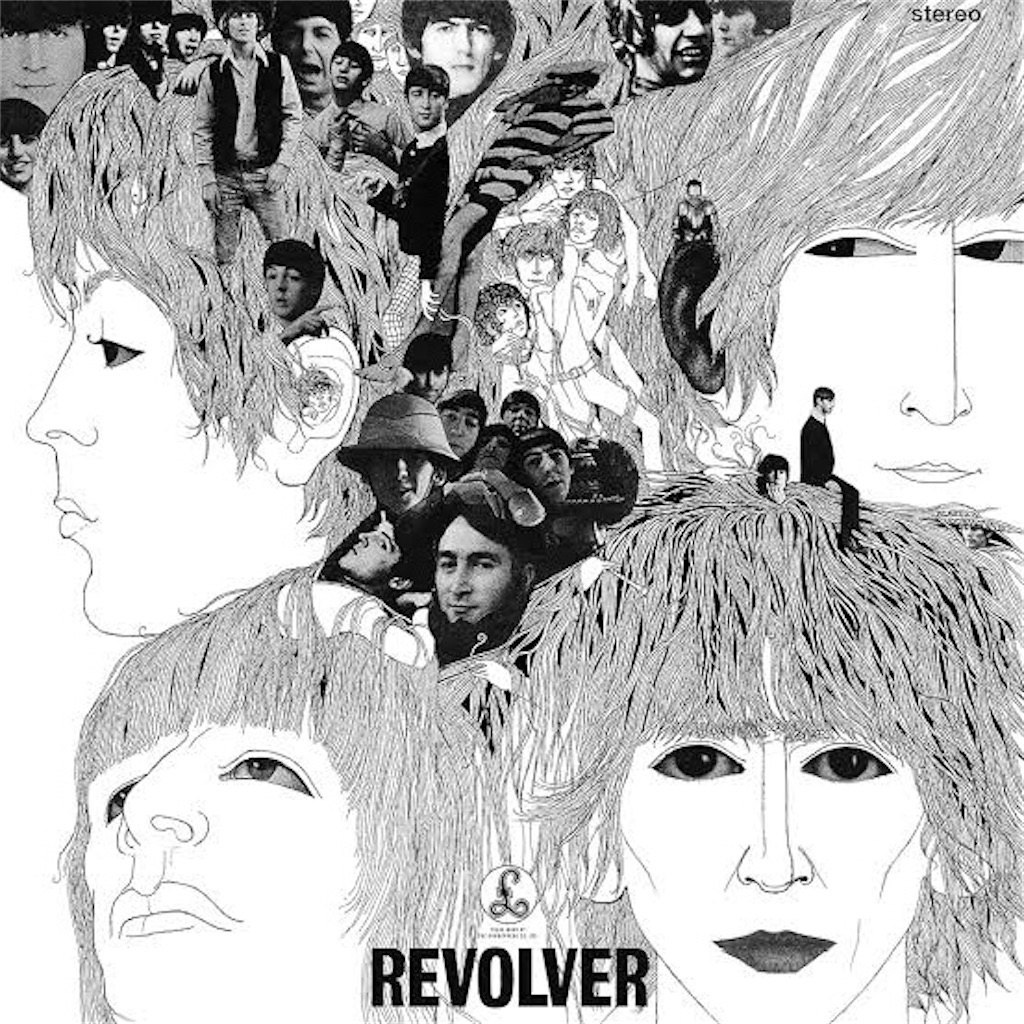
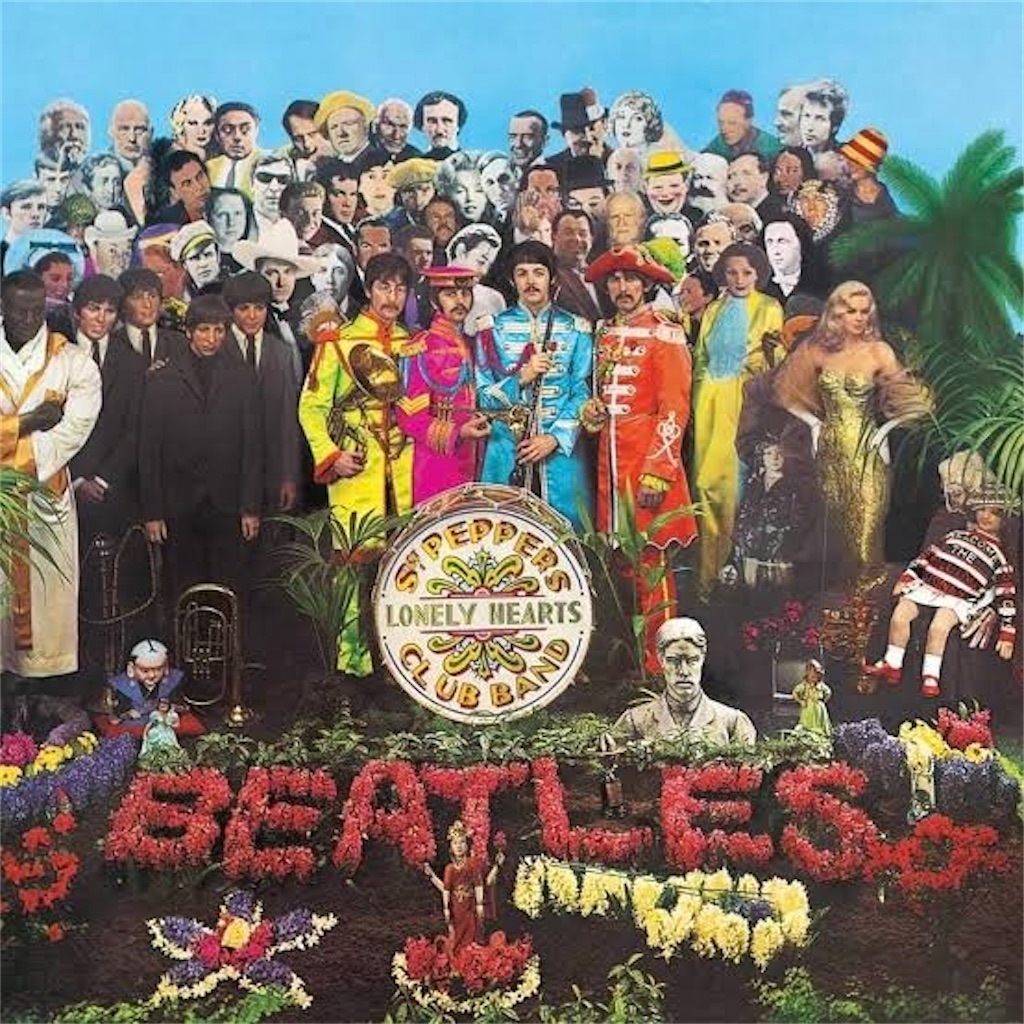
いずれにしても、低迷期のアルバムだなんて、とんでもない。
前々作「ブラック・シー」や前作「イングリッシュ・セトルメント」の評価が一般的に高い訳だが、その流れで当時の人達がXTCに求めていたものと「ママー」は違っていたのだろう。
ライヴ活動の停止から充分なプロモーションが出来なかったということもあったのだろう。
だが、先入観無しに聴いてみると、本当に良いアルバムだ。
個人的には名盤と言われる「スカイラーキング」より好きである。


「ママー」、隠れ名盤に認定しよう!